今回は金利と為替ついてですが、
日本の歴史における金利の起源は、「出挙(すいこ)」であると言われています。
「出挙」とは、稲の貸借のことで、春に稲の種を貸し出して、秋の収穫期に利息として収穫した稲を返すというものです。中国の古くからの慣習を日本でも行なったとされています。
中世の日本は、金融の先進国と言える程、金融の仕組みが発達していました。
ここには出てきませんが日本は村単位でお金を貸し合う仕組みもかなり古い時代からあります。
今の日本ではとても考えられませんが、当時の日本は世界に稀に見るほどの金融先進国でした。
それと為替についですが、為替とは遠隔地の決済を取引する手法で、海外通貨のことではありません。
「為替取引」とは、遠隔地間の貸し借りを決済するのに、現金の輸送ではなく、手形や小切手によって決済する方法のことです。
日本で最初の為替取引は、「替米」であると言われています。「替米」とは、遠隔地に米を送るのに、現物の代わりに送る手形のことです。
中世に入ると、為替取引が発展し、鎌倉時代には将軍に仕えた御家人が鎌倉や京都で米や銭を受け取る仕組みとして為替取引が行なわれていました。
また、諸司・諸家が発行する切下文や返捗という支払方法がありましたが、これが現在の小切手や手形のもとになったとされています。
小切手や手形は信用の代わりとなるもの。現金と変わらないものとして今でも活用されています。
コラムニストについて
- 会社員として勤務しながら副業でビジネス活動を開始。 失敗を繰り返すも這い上がり、通算11年の会社員経験を経て独立。 失敗の経験を生かして、今では多角的にビジネス活動をしており、将来の不安は無くなる。 現在では過去の自分と同じ不安を持つ方に「日本一気軽な相談役」として副業アドバイスを行いながら、将来の為の資産形成の啓蒙活動も行っている。
最新の投稿
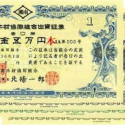 学び2018.04.10直接金融と市場取引を担う金融機関
学び2018.04.10直接金融と市場取引を担う金融機関 学び2018.03.07間接金融と預貯金取扱金融機関
学び2018.03.07間接金融と預貯金取扱金融機関 学び2017.12.11日本の直接金融について
学び2017.12.11日本の直接金融について 学び2017.09.05英米がリードしてきた金融の制度改革
学び2017.09.05英米がリードしてきた金融の制度改革

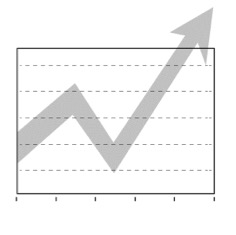 Posted
Posted  金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜
金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その②
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その② 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その①
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その① 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?
生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは? 一切外食をしない
一切外食をしない 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ
生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ ③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック
③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック