2007年から始まったサブプライム問題、そこから拡がった世界金融危機において受けたダメージを緩和するため、世界中の先進国がQE踏み出してからもうじき10年。
この流れに歯止めを掛けようという意欲が、ようやく世界随所で見られる様になってきた。
既に米国は年3回程のから4回程の利上げ政策を立てており、今年の3月にはゼロ金利を脱却を成し遂げている。
現在、これに続こうとQEのテーパリングを目論んでいるのが欧州で、ECBは2018年からの債券等の資産の購入抑制を示唆している。
昨今、欧州は景気が回復してきている事を唄っており、たしかに経済指標の結果も悪くなく、長期金利も上昇傾向にある。
ただ連合体である欧州に関しては、テーパリング、そして利上げという道のりを進むのは、米国以上に困難なものだろう。
ギリシャをはじめとした南欧諸国の財政問題、ドイツに至っても主要銀行の経営難などの騒動は、一時凌ぎの施策により表舞台からなりを潜めてしまった。
これらの要因で、見るに耐えないものとなったであろうバランスシートを少しでもなだらかにするべく、資産購入の抑制という段階に踏み切ろうとした決意は評価に値する。
しかし連合体であるが故に、各国の管理、統制にどうしても穴が生じてしまう事は否めず、歴史上繰り返されている欧州特性の簿外債務の発覚という懸念が頭を過ぎってしまう。
コラムニストについて
- 元外資系保険会社の日本展開スタッフして勤務するも、会社トップの判断で急遽日本展開が白紙になる。 企業に属する不安定さを感じ、企業に属さない「新しいビジネス形態」を確立させるため数十社の企業と業務提携を行い、幅広いお客様のニーズに合わせることのできる知識と商品を持っているため、顧客の満足度は高い。同じ不安を持つ同世代に対して「新しいビジネス形態=自分で年金を作る=資産形成の重要性」を提案。
最新の投稿
 ニュース2017.09.10過剰な北朝鮮への挑発発言、その真の狙いとは・・・
ニュース2017.09.10過剰な北朝鮮への挑発発言、その真の狙いとは・・・ 学び2017.08.08ハードフォークで垣間見る、今後の仮想通貨を巡る変化の兆し
学び2017.08.08ハードフォークで垣間見る、今後の仮想通貨を巡る変化の兆し 学び2017.07.14日本の電器産業M&Aの常連KKRとは
学び2017.07.14日本の電器産業M&Aの常連KKRとは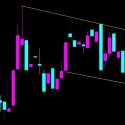 ニュース2017.07.13ついに下された日経225のレギュラー脱落
ニュース2017.07.13ついに下された日経225のレギュラー脱落

 Posted
Posted  金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜
金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その②
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その② 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その①
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その① 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?
生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは? 一切外食をしない
一切外食をしない 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ
生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ ③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック
③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック