ついに日本銀行が設立された時の話です。
今の中央集権金融システムはここからが本当の始まりになりました。
明治政府は、銀行制度の確立を目指して、1872年(明治5年)に米のナショナル・バンク制度にならった「国立銀行条例」を制定し、これに基づき、全国で153の国立銀行が設立されました。名称は国立銀行でしたが、実際は政府とは資本関係のない民間銀行でした。
国立銀行が発行した紙幣は、「国立銀行紙幣」と言い、それぞれの銀行が名前を入れて使っていました。
しかし、1877年(明治10年)に西南戦争が始まると、戦争の資金を調達するために明治政府が大量の不換政府紙幣や不換国立銀行紙幣を発行したことで、貨幣の価値が急落し、激しいインフレが発生します。
インフレを抑えるためには、不換政府紙幣や不換国立銀行紙幣を整理して、通貨価値を安定させる必要があったため、1882年(明治15年)に日本の中央銀行として日本銀行が設立されました。
1885年(明治18年)には銀貨と引換えのできる兌換(だかん)銀券として、現在の紙幣である日本銀行券が発行され、政府紙幣と国立銀行紙幣は、1899年(明治32年)に使用停止となり、わが国の紙幣は日本銀行券に統一されました。
1893年に銀行条例が施行されると、国立銀行の多くは普通銀行に転換します。そして、日清戦争前後の企業設立ブームにのって、数多くの普通銀行がこのときに設立されました。
ところで余談ではありますが、中央銀行である日本銀行は民間である事をご存知でしょうか?
また、1〜500円硬貨の発行元は日本国(国家)、1000円以上の紙幣の発行元は日本銀行(民間)、という違いがあるのも一興ですね。
コラムニストについて
- 会社員として勤務しながら副業でビジネス活動を開始。 失敗を繰り返すも這い上がり、通算11年の会社員経験を経て独立。 失敗の経験を生かして、今では多角的にビジネス活動をしており、将来の不安は無くなる。 現在では過去の自分と同じ不安を持つ方に「日本一気軽な相談役」として副業アドバイスを行いながら、将来の為の資産形成の啓蒙活動も行っている。
最新の投稿
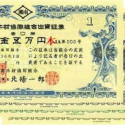 学び2018.04.10直接金融と市場取引を担う金融機関
学び2018.04.10直接金融と市場取引を担う金融機関 学び2018.03.07間接金融と預貯金取扱金融機関
学び2018.03.07間接金融と預貯金取扱金融機関 学び2017.12.11日本の直接金融について
学び2017.12.11日本の直接金融について 学び2017.09.05英米がリードしてきた金融の制度改革
学び2017.09.05英米がリードしてきた金融の制度改革

 Posted
Posted  金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜
金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その②
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その② 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その①
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その① 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?
生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは? 一切外食をしない
一切外食をしない 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ
生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ ③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック
③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック