みなさん、こんにちは。
東京、渋谷某所で“お金の学校”を運営しているコレキヨです。
今回のコラムでは、“不公平な消費税”についてお話ししていこうと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
・・・・
前回お伝えした続き、消費税について言われる問題点として、
1.逆進的、2.益税、3.消費意欲の低下、とお伝えしたが、最後の4つ目は、消費税の転嫁である。
これは中小零細の事業者が顧客に消費税を転嫁できないという問題であるが、つまり全てのしわ寄せは事業者の営業利益から自腹を切ることであり、それは廃業へ追いやる危険性へつながっていく。
一般に消費税は消費者が納めると考えられているが、現実の消費税法には、消費税の納税義務者は事業者だと定められている。
(事業者がものを売る、その時お客さんから消費税を預かる。そして、預かった消費税を事業者自身が納税義務者として納める形になっている。納税義務者が、お客さんにそれを転嫁できるかできないかまでは、消費税法がきちんと定めているわけではない。)
つまり、どういうことか。
競争力の弱い事業者、卸業者は大企業の下請として仕事をする。パワーバランスは大企業が大きいことは常で、例えば、定価プラス消費税といって請求すると「もうお前のところには仕事を頼まない」となるに決まっている。
ということは、その分を飲むしかないわけだが、だからといって、納税義務者であることを免除はされないわけで、自腹を切って納めることになる。
10%になったら、それら企業はどうなってしまうのか。容易に想像がついてしまう。
更に、
消費税が「広く、薄く、公平」であるという「大ウソ」はつづく。
大企業はそのパワーバランスを利用して、消費増税で大儲けしているという。
そもそも、消費増税は商売する企業は賛成出来ない。なぜなら、消費意欲が低下することで、売上が立たなくなり、経営が圧迫されるからだ。
しかしながら、大儲けしているとはどういう事なのか。
そして、政府が言う、「消費増税やむなし」という言葉。それをただ鵜呑みにうることなく、その真意を探る必要がありそうだ。
ここについてはまた、次回に記載していきたい。
・・・・
さてさて、
いかがでしたでしょうか?
このコラムを通じて、
新たな気づきが得られるような情報を
定期更新していければと思っております♬
また次回も是非お楽しみに!
校長コレキヨ
コラムニストについて
- 元医療従事者として勤務するも、直属の上司を見た時に出世後の自分を想像して強烈な不安感を覚える。 「将来の不安=資産で解決が可能」と考え25歳から資産形成の勉強を開始。 2015年からは「お金の勉強会」と称したセミナーを開講。 自ら講師として現在200名の塾生に熱弁を振るう。 実体験が元になっているセミナーは好評で、塾に参加を希望する者は後を絶えない。
最新の投稿
 学び2019.03.16短期投資の優位性
学び2019.03.16短期投資の優位性 学び2019.03.15暗号通貨の利確で納税確定
学び2019.03.15暗号通貨の利確で納税確定 学び2019.03.14その配当は幻想です
学び2019.03.14その配当は幻想です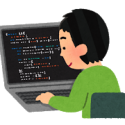 学び2019.03.13アイディアをカタチに
学び2019.03.13アイディアをカタチに

 Posted
Posted  金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜
金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その②
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その② 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その①
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その① 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?
生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは? 一切外食をしない
一切外食をしない 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ
生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ ③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック
③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック