みなさん、こんにちは。
“お金の学校”を運営しているコレキヨです。
今回のコラムでは、“企業分析の定性分析~前編~ ”をお話し
していこうと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
・・・・
今回から実際に企業に投資する際において、自ら集めた情報を使えるようにするために、情報分析の仕方、指標の見方などを見ていきたいと思います。これを理解することで、その時の企業の経営状況や株価の状態を把握できるようになります。
通常、企業分析をする際には、まず定性分析で企業がどういう環境に置かれていてどんな戦略を立てているのか、何が課題なのかを大雑把に掴みます。そして、次に定量分析で財務指標などの細かい数字を追っていきます。 いきなり定量分析でやみくもに数字をいじると、分析に時間がかかる上、大事なところを見落とす可能性があるので、定性分析、続いて定量分析という順に分析をしたほうが効率的です。
それでは、今回は数字を使わない「定性分析」について掘り下げたいと思いますが、これはマクロ環境における成功要因に対して、その企業の経営戦略が合致しているかどうかを分析します。
①企業の置かれている環境分析(PEST分析)
先ず、主に投資先企業の業界に影響を与える要素に注目します。
■経済の変化 景気動向はどうか?金利水準はどうか?
■社会の変化 人々の消費嗜好に変化はないか?人口構成が変わっていくか?流行は何か?
■政治・法律の変化 政治・法律が変わることで製造、流通、販売、アフターサービスに影響はないか?
■技術の変化 革新的な技術によって、これまでの商品を代替されないか?あるいは代替できるか?
②業界構造分析
次は、企業が属している業界の構造を分析します。業界の魅力度、競争状態が激しいかどうか、業界としての課題などを抽出します。
- 新規参入の脅威
新規参入が容易な業界は、収益性の低下を招きやすくなります。一方で、新規参入が難しい業界は、既存企業にとっては有利に働く場合があります。新規参入の脅威があると、業界が低価格設定をして利益率を低下させたり、投資の抑制をして成長性を低下させる可能性が高くなります。
- 代替品の脅威
自社製品よりも対費用効果で優れた製品や、従来機能を全く異なる媒体で代替できると自社の競争力低下に繋がります。場合によっては淘汰されてしまいます。
- 買い手の交渉力
製品の差別化ができないとか、買い手の情報量が多い場合は買い手の交渉力が強くなります。例えば、電化製品や日用品には買い手の交渉力が強くなる傾向があります。
買い手の交渉力が大きいと、安値販売による利益率の低下につながります。また、代金回収が遅くなることで、売上債権回転率の低下につながったり、商品の売れ行きが良くなくなって、棚卸資産回転率の低下につながる可能性もあります。
- 売り手の交渉力
業界を少数企業により寡占している場合に売り手の交渉力が強くなります。例えば、その企業特有の技術を用いた製品や特許によって権利を保護された製品の場合、売り手の交渉力が強くなります。売り手の交渉力が大きいと、仕入の際に相手が代金回収を早く求めてくる可能性があるので買入債務回転率が大きくなる場合があります。
- 業界競合他社
業界内の競争状態が激しいほど、業界の魅力度は小さくなります。業界競合他社との激しい競争は、利益率の低下はもちろん、稼働率を上げて業績を上げようという傾向により、総資産回転率(売上高/総資産)や有形固定資産回転率(売上高/有形固定資産)が高くなってくることがあります。
つづいて、③企業の戦略分析についてですが、、
これについては、また次回追っていきましょう!
投資先企業そのものの経営や戦略を分析していきますので、これも欠かせない定性分析の一つです。是非知っておいていただければと思います!
・・・・
さてさて、いかがでしたでしょうか?
このコラムを通じて、新たな気づきが得られるような情報を定期更新していければと思っております♬
また次回も是非お楽しみに!
コラムニストについて
- 元医療従事者として勤務するも、直属の上司を見た時に出世後の自分を想像して強烈な不安感を覚える。 「将来の不安=資産で解決が可能」と考え25歳から資産形成の勉強を開始。 2015年からは「お金の勉強会」と称したセミナーを開講。 自ら講師として現在200名の塾生に熱弁を振るう。 実体験が元になっているセミナーは好評で、塾に参加を希望する者は後を絶えない。
最新の投稿
 学び2019.03.16短期投資の優位性
学び2019.03.16短期投資の優位性 学び2019.03.15暗号通貨の利確で納税確定
学び2019.03.15暗号通貨の利確で納税確定 学び2019.03.14その配当は幻想です
学び2019.03.14その配当は幻想です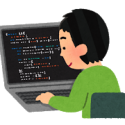 学び2019.03.13アイディアをカタチに
学び2019.03.13アイディアをカタチに

 Posted
Posted  金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜
金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その②
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その② 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その①
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その① 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由
変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?
生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは? 一切外食をしない
一切外食をしない 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ
生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ ③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック
③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック